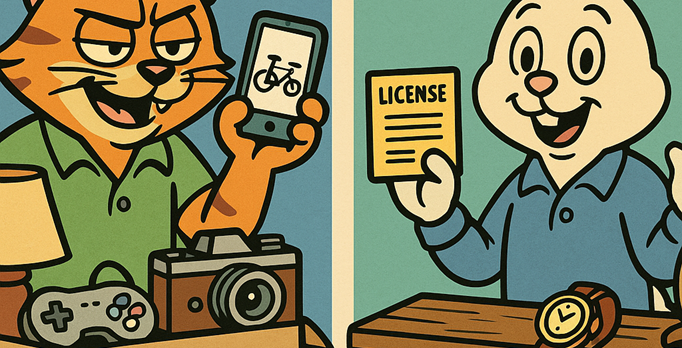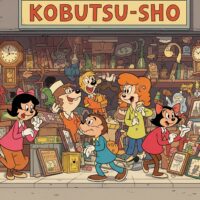「この服、もう着ないからフリマアプリで売っちゃおう!」 「せっかくなら、安く仕入れて高く売る『せどり』で副収入を得たいな」
スマホ一つで、誰もが簡単にモノの売り買いを楽しめる時代。その手軽さから、フリマアプリでの取引にハマっている方も多いのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。その取引、もしかしたら法律違反になっているかもしれません。
「え、趣味でやってるだけなのに?」 「自分の不用品を売ってるだけだよ?」
そう思ったあなた、実はその「だけ」という認識が、思わぬ落とし穴になることがあるのです。
こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。私が店長だった頃、店内には新刊の小説の隣に味わい深い古書が、流行りのキャラクターグッズの隣に一点ものの古着が並んでいました。そんな風に、新旧問わず面白いモノを集めて「お店」を作るのは、本当にワクワクする仕事です。
だからこそ、その大切な「お店」とあなた自身を、法律というルールでしっかり守ってほしい。この記事は、あなたのフリマライフやお店作りが、もっと楽しく、もっと安全になるための「お守り」のようなお話です。古物商許可のキホンのキ、一緒に見ていきましょう!

そもそも「古物商許可」って、なんで必要なの?
「許可」と聞くと、なんだか面倒で堅苦しいイメージがありますよね。でも、この古物商許可には、ちゃんとした大切な役割があるんです。
それは、盗品が市場に流通するのを防ぐため。
もし、盗まれたものが簡単にフリマアプリやリサイクルショップで売買できてしまったら、犯罪はなくなりませんよね。そこで、中古品(法律では「古物」といいます)をビジネスとして取り扱う人には、警察署にきちんと届出をして許可をもらい、取引のルールを守ってもらう仕組みになっています。これが、古物営業法という法律で定められた古物商の制度です。
つまり、この許可は、あなた自身が「私は怪しい取引はしませんよ」ということを証明し、お客様に安心して買い物をしてもらうための信頼の証でもあるのです。
【セルフチェック】許可が必要な人と、そうでない人
では、具体的にどんな場合に許可が必要になるのでしょうか。ここが一番気になるところですよね。ポイントは、**「ビジネス(営業)として、転売目的で仕入れた古物を売買するかどうか」**です。

許可が【不要】なケース(セーフ!)
- 自分の不用品を売る 例:「自分で使うために買ったけど、結局使わなかった服」「読み終わった本」など。初めから転売目的で買ったものではないので、許可は必要ありません。
- 無償でもらったものを売る 例:「友人からタダで譲り受けた家具」など。仕入れにお金がかかっていないので「営業」にはあたりません。
- 自分が海外で買ってきたものを売る 例:「海外旅行のお土産で買いすぎた雑貨」など。日本の古物営業法は、国内での盗品流通を防ぐためのものなので、対象外です。
許可が【必要】なケース(アウトかも!)
- 転売する目的で、中古品を仕入れて売る 例:「リサイクルショップやフリマアプリで安く仕入れた商品を、利益を上乗せして販売する」こと。これは、いわゆる「せどり」のことで、継続的に行う場合は完全に古物営業にあたります。
- 仕入れた中古品を、修理したり部品取りしたりして売る 例:「壊れたアンティーク時計を仕入れて修理して販売する」など。
- 仕入れた中古品を、レンタルに出す 例:「古着を仕入れて、ファッションレンタルサービスを行う」など。
- 国内で仕入れた古物を、海外に輸出して販売する インターネットを通じて海外に販売する場合も、国内での仕入れ行為が規制の対象となります。
「趣味の範囲」だと思っていても、利益を出す目的で継続的に仕入れと販売を繰り返していれば、それは立派な「営業」です。無許可営業には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則もありますので、注意が必要です。
古物商許可、自分で申請できる?取得までのロードマップ
「自分は許可が必要かも…」と思った方、ご安心ください。古物商の許可申請は、ポイントさえ押さえれば、自分でチャレンジすることも可能です。
STEP1:申請する場所を確認しよう
古物商許可の申請窓口は、あなたのお店の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。お店といっても、店舗は必須ではありません。自宅を営業所として申請することも可能です。
STEP2:許可の条件をクリアしているかチェック!
誰でも許可が取れるわけではなく、いくつかの条件があります。
- 人的要件(欠格事由) 古物営業法第4条には「許可が受けられない人」の条件(欠格事由)が定められています。簡単に言うと、「過去に一定の犯罪で刑罰を受けてから5年経っていない」場合や、「暴力団員である」場合などが該当します。詳しくは警視庁のウェブサイトにも記載がありますので、不安な方は一度確認してみてください。 ▶ 参考リンク:警視庁 古物商許可申請
- 場所的要件(営業所) 古物を管理・保管する場所として「営業所」を定める必要があります。これは、自宅でも問題ありません。ただし、賃貸物件や集合住宅の場合は注意が必要です。賃貸契約書で事業利用が禁止されていたり、マンションの管理規約で営業活動が禁止されていたりする場合があります。事前に大家さんや管理組合に確認しておきましょう。
STEP3:必要書類を集めよう!
申請に必要な書類は、個人の場合と法人の場合で異なります。ここでは代表的なものを紹介します。
| 書類名 | 主な取得場所 | 備考 |
| 許可申請書 | 警察署のウェブサイト等 | 申請する警察署で事前にもらうのが確実 |
| 住民票の写し | 市区町村の役所 | 本籍地記載のもの。マイナンバーは不要 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村の役所 | 運転免許証のことではありません |
| 略歴書 | – | 過去5年間の職歴などを記載 |
| 誓約書 | – | 欠格事由に該当しないことを誓約する書類 |
| URLを届出る書面 | – | 自分のHPやフリマアプリのプロフィールページのURLを届け出る場合 |
※これはあくまで一例です。詳細は必ず管轄の警察署にご確認ください。
STEP4:いざ、警察署へ!
書類がすべて揃ったら、管轄の警察署に提出します。その際に申請手数料として19,000円が必要です。申請後、審査に約40日かかります。この期間に、警察署の担当者が営業所の確認に来ることもあります。
祝・許可取得!でも、その後に守るべき大切なルール
無事に許可証が手に入ったら、いよいよプロの古物商として営業スタートです!しかし、許可はゴールではありません。信頼されるお店であり続けるために、守るべき大切な義務があります。
- 標識の掲示 許可証と一緒に交付される「古物商許可プレート(標識)」を、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
- 本人確認 1万円以上の商品を買い取る際は、原則として相手の身分証明書(運転免許証など)で本人確認を行う義務があります。
- 古物台帳への記録 「いつ、誰から、何を」買い取ったか、または売ったかを記録する帳簿(古物台帳)を作成・保管する必要があります。これを怠ると、いざ盗品が見つかった時に大変なことになります。私が店長だった頃も、どの古書を誰から仕入れたか、きちんと記録していました。これがお店の信用を守るのです。 ▶ 参考リンク:e-Gov法令検索 古物営業法
- 不正品の申告 買い取ろうとした品物が「もしかして盗品かも?」と疑わしい場合は、直ちに警察に申告する義務があります。
これらの義務は、どれも「盗品の流通防止」という本来の目的に繋がっています。
まとめ:古物商許可は、あなたのビジネスの「お守り」です
フリマアプリでの取引から、本格的な古物商としての開業まで。その一歩を踏み出す時、古物商許可は、あなたを法的に守り、お客様からの信頼を高めてくれる、とても心強い「お守り」のような存在です。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつのルールには、きちんと理由があります。この記事が、あなたの次の一歩を後押しできれば、これほど嬉しいことはありません。
お店の種類や状況によって必要な準備や注意点は様々です。もし「自分の場合はどうなんだろう?」「書類作りがやっぱり不安…」といった具体的なご相談やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたのワクワクするお店作りを、全力でサポートさせていただきます。
【ご注意】 この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。