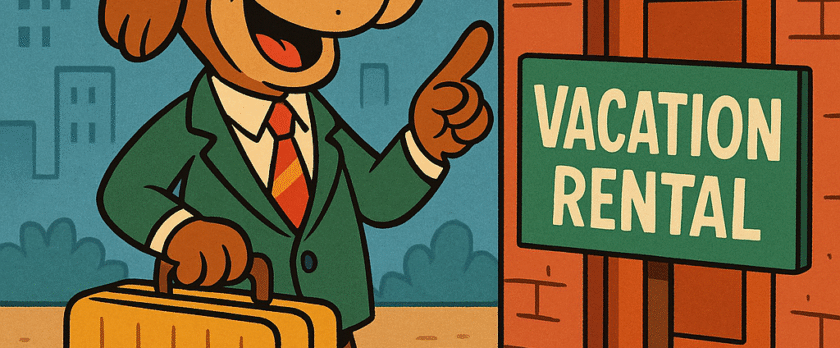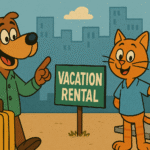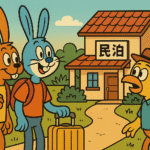みなさん、こんにちは!元「遊べる本屋」店長、そして現役行政書士の栗原です。
突然ですが、みなさん、お家で眠っているお部屋や、実家の空き家、どうにか有効活用できないかなぁ…なんて考えたことありませんか?そんな時、ふと頭をよぎるのが「民泊」ですよね。最近では、インバウンド需要の回復もあって、「副業で民泊ってどうなんだろう?」と興味を持たれている会社員の方も多いのではないでしょうか。
「なんだか儲かりそうだけど、なんか難しいそう…」「そもそも法律とか大丈夫なの?」そんな疑問をお持ちのアナタ!ご安心ください。行政書士として、そして会社員時代に「遊べる本屋」をゴリゴリ運営していた経験を持つ栗原が、会社員が副業で民泊を始める際の現実的なメリット・デメリット、そして見落としがちな注意点まで、バッチリ解説していきます。
この記事を読めば、あなたの民泊開業への一歩が、きっとクリアに見えてくるはずです!


会社員が副業で民泊を始めるって、どういうこと?
「民泊」と一言で言っても、実はいくつか種類があるんです。大きく分けて、次の3つが挙げられます。
- 住宅宿泊事業法に基づく民泊(いわゆる「新法民泊」)
- 旅館業法に基づく簡易宿所営業
- 国家戦略特別区域法に基づく特定認定事業(いわゆる「特区民泊」)
会社員の方が副業として検討する場合に一番現実的なのが、やはり住宅宿泊事業法に基づく民泊でしょう。これは、年間180日を上限として、自宅の一部や所有するマンション・戸建てなどを活用して旅行者に宿泊サービスを提供するものです。申請の手続きを行政に届け出ることで始めることができます。
「え、たった180日?」と思うかもしれませんが、会社員の方にとっては本業との兼ね合いを考えると、この日数制限が逆にメリットになることも多いんです。
副業民泊のココが魅力!会社員に嬉しい3つのメリット
では、会社員が副業で民泊を始めるメリットを具体的に見ていきましょう。
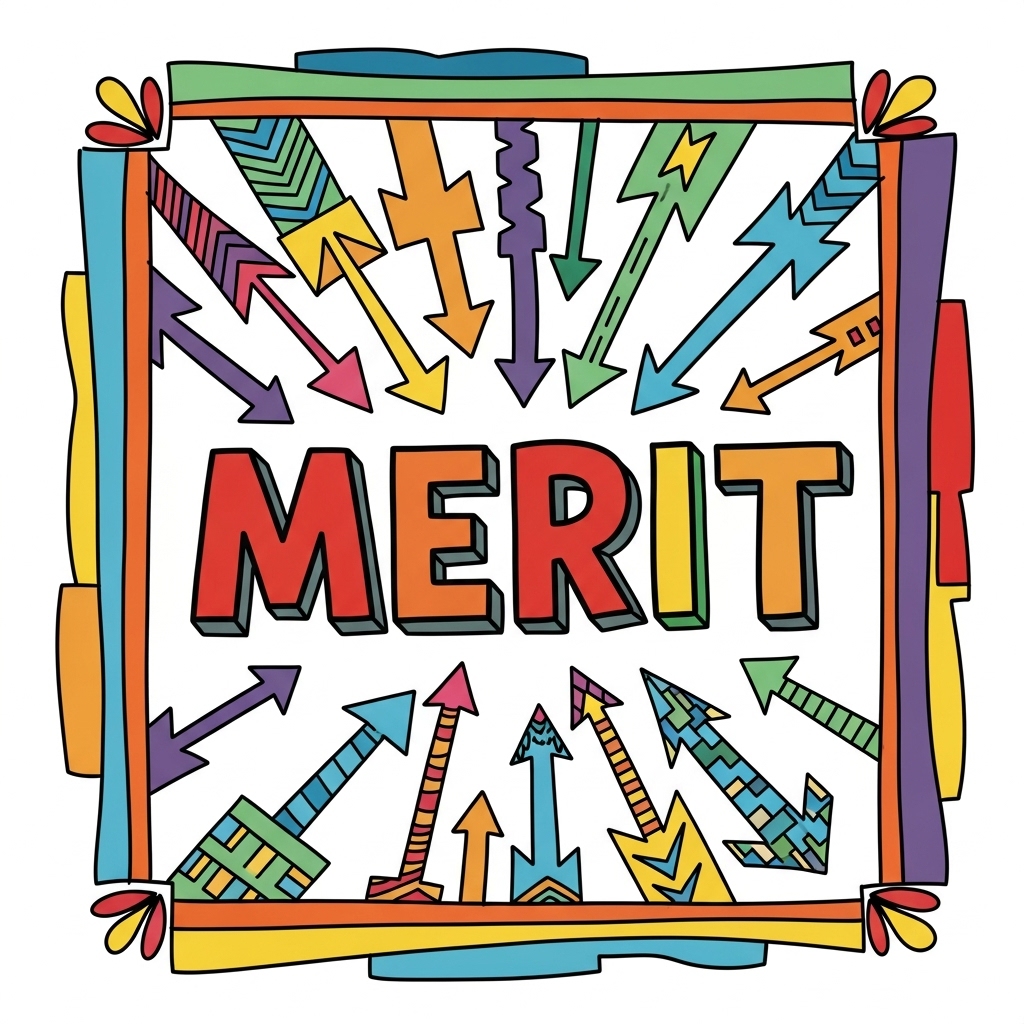
1. 収入源の多様化と不労所得への期待
なんと言っても一番の魅力はこれですよね!毎月の給料以外に収入の柱ができるというのは、経済的な余裕だけでなく、精神的な安心感にも繋がります。本業の収入が不安定な時代だからこそ、複数の収入源を持つことの重要性は増しています。
民泊は、初期投資(物件取得費、改修費、家具家電購入費など)こそかかりますが、一度物件を整えてしまえば、あとは宿泊費という形で継続的に収益を生み出すことができます。例えば、あなたが会社で会議をしている間にも、旅先のゲストがあなたの部屋でくつろぎ、その宿泊費が収益となる、といった具合です。これは、まさしく「不労所得」への第一歩と言えるでしょう。
うまく集客ができ、運営が軌道に乗れば、本業の収入に大きくプラスアルファをもたらし、旅行や趣味に使えるお金が増えたり、将来のための貯蓄を加速させたり、あるいは住宅ローンの返済に充てたりすることも夢ではありません。賢い投資として、将来の資産形成にも繋がる可能性を秘めているんです。
2. 空き家や遊休資産の有効活用と資産価値の向上
ご実家が空き家になっている、使っていない部屋がある、住み替えで以前の家が空いている、なんて方には朗報です。ただ空き家にしておくだけでは、固定資産税や維持管理費がかかるばかりでなく、建物が劣化するスピードも速まります。しかし、それが民泊として活用できれば、家賃収入を得ながら、建物の維持管理も兼ねることができ、さらに資産価値の低下を防ぐことにも繋がります。
特に地方にある空き家などは、解体費用もバカになりませんし、かといって売却も難しいケースがありますよね。そんな時、民泊として再生させることで、その物件に新たな価値を与え、地域の活性化にも貢献できる可能性があります。例えば、歴史ある古民家を改装して民泊にすることで、その土地ならではの文化体験を提供し、特別な宿泊施設として生まれ変わらせることも可能です。物件を所有している方にとっては、まさに一石二鳥、いや三鳥くらいのメリットがあるのではないでしょうか。
具体的な遊休資産の活用例としては、以下のようなものが考えられます。
- 長期出張中の自宅の一部:期間を限定して貸し出し、出張中の家賃負担を軽減。
- 子育てを終えて空いた子供部屋:使わない空間を有効活用し、ゲストに新たな体験を提供。
- 相続した地方の古民家:地域の魅力を発信する拠点として、観光客を呼び込む。
- 使っていない別荘やセカンドハウス:利用しない期間に貸し出すことで、維持費を賄いながら、多様なゲストとの出会いを楽しむ。
3. コミュニケーション能力の向上と国際交流の機会
民泊運営は、ゲストとのやり取りが不可欠です。予約の受付からチェックイン・アウト、滞在中の質問対応、トラブル対応まで、多岐にわたるコミュニケーションが発生します。時には予想外の事態に直面することもあるでしょう。これらを通じて、自然と相手のニーズを汲み取る力、問題解決能力、そして臨機応変に対応する力が養われます。これは、会社での業務にも必ず活きてくるスキルです。
また、近年のインバウンド需要の高まりもあって、海外からのゲストを受け入れる機会も非常に多いでしょう。異なる文化や習慣を持つ人たちと触れ合うことは、あなたの視野を広げ、異文化理解を深める貴重な経験となります。時には拙い英語や身振り手振りでのやり取りになるかもしれませんが、そうした経験が語学力アップのモチベーションにも繋がり、新たな出会いがあなたの人生を豊かにしてくれるはずです。普段の会社生活ではなかなか得られない、刺激的な体験ができるのも民泊の醍醐味と言えるでしょう。
見て見ぬふりはNG!副業民泊の3つのデメリットと注意点
良いことばかりではありません。会社員が副業で民泊を始めるには、それなりのデメリットと注意すべき点があります。これらを理解せずに始めると、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。

1. 時間的制約と本業への影響
会社員の一番のネックはやはり「時間」です。民泊の運営には、清掃、問い合わせ対応、鍵の受け渡し、トラブル対応など、意外と多くの時間と労力がかかります。
- 清掃・リネン交換: 宿泊者が入れ替わるたびに、部屋の清掃やリネン類の交換が必要です。ゲストの満足度を左右する重要な部分なので、手を抜くことはできません。自分でやる場合は休日の時間を大幅に費やすことになりますし、専門の業者に委託する場合はその費用がかさみます。
- 問い合わせ対応: ゲストからの予約や、滞在中の質問は、昼夜を問わず来る可能性があります。迅速な対応が求められるため、仕事中でもスマートフォンが手放せなかったり、緊急時には対応を迫られたりする場面も出てくるでしょう。
- トラブル対応: 設備の故障(給湯器の故障、エアコンの不具合など)、騒音、ご近所トラブル、ゲストの体調不良など、いつ何が起こるか分かりません。緊急時には、本業を休んで駆けつける必要が出てくる可能性もあります。
これらの対応をすべて自分で行うとなると、本業との両立はかなり難しいでしょう。どこまでを自分でやるか、どこからを外部に委託するか、管理体制を事前にしっかり計画することが重要です。
2. 法規制、複雑な申請手続き、そして税金の問題
民泊を始めるには、適切な法律に基づいた申請や届出が必要です。「民泊」という言葉が一般的になったからといって、勝手に始めて良いわけではありません。
特に、会社員の方が副業で始める場合に多い「住宅宿泊事業法」に基づく民泊であっても、都道府県知事への届出が必要です。さらに、消防法や建築基準法、景観法など、他の法律も関係してきます。地域の条例で独自の規制(営業可能区域の制限、最低宿泊日数、周辺住民への説明義務など)を設けている自治体も少なくありません。
「申請とか法律とか、なんか難しい…」そう感じる方も多いでしょう。たしかに、慣れない方にとっては煩雑に感じるかもしれません。しかし、これらをきちんとクリアしなければ、違法な民泊として罰則の対象となる可能性もあります。最悪の場合、刑事罰や多額の追徴課税といった事態になりかねません。
そして、副業で収入を得る以上、切っても切り離せないのが「税金」です。民泊で得た収入は、原則として不動産所得または事業所得として確定申告が必要です。会社員の方の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。民泊運営にかかる経費(清掃費用、消耗品費、光熱費、修繕費、広告宣伝費、廃棄物処理費用など)をきちんと計上することで、所得税や住民税の負担を軽減することができますが、これらの会計処理も難しいと感じるかもしれません。
【知っておきたい!関連法令のチェックポイント】
- 住宅宿泊事業法: 民泊を始める上での基本的なルールを定めています。宿泊日数(年間180日)の上限や、住宅宿泊事業者としての届出義務などが規定されています。参考:観光庁 住宅宿泊事業法について
- 消防法: 宿泊施設としての安全性を確保するため、消火器の設置や誘導灯の設置など、消防設備の基準が設けられています。
- 建築基準法: 建物が安全基準を満たしているかを確認します。用途変更が必要な場合もあります。
- 自治体の条例: 各自治体によっては、民泊の運営に関する独自のルールを定めている場合があります。必ず、物件所在地の自治体のウェブサイトで確認しましょう。例:東京都における住宅宿泊事業の届出について
これらの法律や条例について、自分で調べて完璧に理解するのはなかなか大変です。不安な場合は、専門家である行政書士や税理士に相談することをお勧めします。
3. 近隣トラブルと地域住民との関係性
民泊運営で意外と多いのが、近隣住民とのトラブルです。不特定多数の宿泊客が出入りすることへの不安感、深夜の騒音、ごみの不法投棄など、近隣住民にとってはストレスになることがあります。
- 騒音対策: 夜間のパーティーや大声での会話、深夜のチェックイン・アウト時の物音など、騒音に関する注意喚起を徹底する必要があります。事前にハウスルールを作成し、ゲストに周知徹底することが重要です。
- 事業系ごみの処理: 民泊で出たごみは、一般のごみ収集では回収されません。自治体のごみ収集ルールとは異なり、事業系ごみとして専門の廃棄物処理業者と契約し、適切に処理する必要があります。この点をおろそかにすると、ご近所トラブルの原因となるだけでなく、違法行為となる可能性もあります。
- 緊急時の連絡先: 万が一のトラブルに備え、近隣住民がすぐに連絡できる緊急連絡先(あなた、または代行業者)を明確に提示するなど、誠実な対応が求められます。
良好な関係性を築くためには、開業前に近隣住民へ丁寧に説明し、理解を得る努力をしましょう。ご近所付き合いも、一種の集客活動と捉えるくらいの心構えが大切です。地域との共存なくして、安定した民泊運営は難しいと言えるでしょう。
副業民泊、成功へのカギは「管理」と「準備」!
会社員が副業で民泊を成功させるためには、いかに「効率的な運営管理体制を築けるか」と「事前の準備をしっかり行うか」がカギとなります。
1. 運営管理はアウトソーシングも視野に
時間的制約が大きい会社員の場合、清掃や問い合わせ対応などを専門の民泊運営代行会社に委託するのも賢い選択です。手数料はかかりますが、その分、本業に集中でき、質の高いサービスをゲストに提供できます。
「運営」や「管理」をどこまで自分でやり、どこからプロに任せるか、収支シミュレーションをしながら検討しましょう。
2. 開業前の徹底したリサーチと計画
「始め方」を間違えると、後々苦労することになります。
- 物件のリサーチ: ターゲットとする客層(インバウンド、国内旅行者、ビジネス客など)に合った立地か、競合物件はどうか。
- 法規制の確認: 物件所在地の自治体の条例まで細かく確認し、必要な許可や申請は何かを明確にする。
- 資金計画: 初期投資(物件取得費、改修費、家具家電購入費など)と運営費用(清掃費、光熱費、消耗品費、保険料、廃棄物処理費用など)を綿密に計画する。
- 集客戦略: どの予約サイト(OTA)を利用するか、独自のウェブサイトを作るかなど、集客方法を検討する。
これらを事前にしっかり行い、無理のない開業計画を立てることが重要です。
3. 周囲への説明と理解を得る努力
前述の通り、近隣住民とのトラブルは避けたいものです。開業前に、自治会や近隣住民に民泊を始めることを説明し、理解を得る努力をしましょう。緊急連絡先を伝える、事業系ごみの適切な処理方法を明示するなど、誠実な対応が信頼関係を築く第一歩です。
まとめ:会社員民泊は「計画と覚悟」があればアリ!
会社員が副業で民泊を始めることは、決して「難しい」ことではありません。しかし、安易な考えで始めると、時間や手間、トラブルに追われ、本業にも影響が出てしまう可能性があります。
収入増、空き家活用、国際交流といった魅力的なメリットがある一方で、時間的制約、法規制・税金、近隣トラブルといったデメリットや注意点も存在します。
大切なのは、これらのメリット・デメリットをしっかり理解し、「自分にとって何が一番重要か」「どこまでなら対応できるか」を明確にした上で、事前準備と計画を徹底することです。
そして何より、「遊べる本屋」で店長をしていた頃、私も常に意識していたことですが、「楽しんで、誠実に、そして法律は守って商売をする!」という気持ちが、成功への一番の近道ではないでしょうか。
許認可申請でお悩みですか?お気軽にご相談ください!
民泊の始め方で不安がある、許可申請について詳しく知りたい、といった方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの状況に合わせて、必要な手続きや注意点について丁寧にご説明させていただきます。
こちらもご確認ください。→民泊事業申請について
【ご注意】 この記事は、2025年5月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。民泊の開業・運営にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。