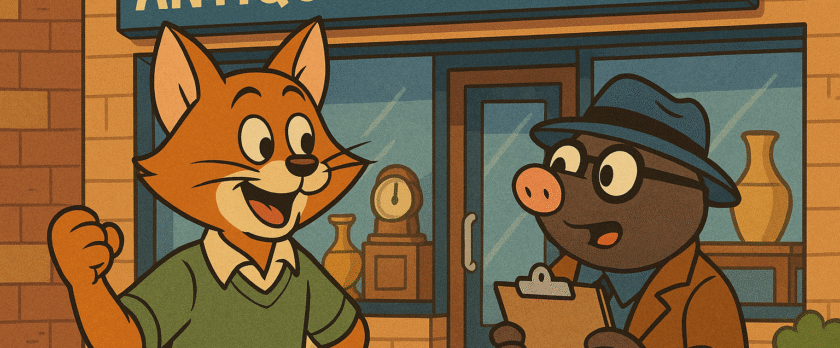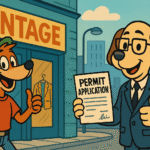古物商の許可申請の準備を進めていると、ふと現れる「管理者」という役職。
「ん?管理者って、お店の店長のこと?」 「個人でやるなら、自分がなればいいのかな?」 「そもそも、どんな重要な役割があるの?」
こんな風に、首をかしげている方も多いのではないでしょうか。
こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。私が店長だった頃、もちろんお店の売上やスタッフのシフトを管理していました。しかし、それと同時に、古物営業法という法律のルールを守るための、もう一つの顔…法律上の「管理者」という重要な役割も担っていたのです。
そう、「店長」と「古物商の管理者」は、似ているようで全くの別物。そして、この管理者を誰にするかは、許可申請の成否を分ける、非常に大切なポイントなのです。
今回は、この少し分かりにくい「古物商の管理者」について、その正体から失敗しない選び方まで、元店長の現場目線で徹底的に解説していきます!

そもそも古物商の「管理者」とは?店長や社長とは違うその役割
まず、多くの方が混同しがちな「店長」と「管理者」の違いから、ハッキリさせておきましょう。
- 店長(店舗責任者など): 売上を上げ、お客様に喜んでもらい、スタッフをまとめる「攻め」の司令塔。
- 古物商の管理者: 法律を遵守し、不正な取引がないか監督する「守り」の要。
このように、立場は全く異なります。社長や許可者本人が管理者を兼ねることも多いですが、役割としては別物と理解してください。
管理者の役割は「法律を守る現場監督」
法律(古物営業法)では、「管理者」を「営業所に係る業務を適正に実施するための責任者」と定めています。 具体的には、その営業所で行われる古物の取引が、法律のルールから外れていないかを監督し、もし違反がありそうな場合はそれを止めさせ、従業員に正しいやり方を指導する、いわば「法律遵守の現場監督」なのです。だからこそ、古物商の管理者は、許可を得る上で欠かせない存在とされています。
なぜ管理者の選任が法律で義務付けられているのか
なぜなら、古物商の許可は、警察署が盗品の流通を防ぐために与えるものだからです。許可者本人(社長など)が常に現場にいるとは限りませんよね。そこで、各営業所に必ず一人の「現場責任者(管理者)」を置くことで、日々の営業がきちんと法律に則って行われていることを担保しているのです。これは、ビジネスの信頼性を保つ上でも非常に重要な役割です。
誰が管理者になれる?気になる資格要件と失敗しない選び方
では、具体的に「誰が管理者になれるのか」、そして「誰を選ぶべきなのか」。ここでは、管理者の選び方の核心に迫ります。
管理者になるための「3つの資格要件」
古物商の管理者になるには、特別な資格は必要ありませんが、クリアすべき最低限の条件があります。
- 欠格事由に該当しないこと: 許可を受ける本人と同様に、管理者も「過去に特定の犯罪で刑罰を受けてから5年経っていない」などの欠格事由に当てはまる人はなれません。
- 未成年者でないこと: 原則として、業務を適正に実施できる能力が求められるため、成年である必要があります。
- その営業所に常勤できること: これが非常に重要なポイントです。管理者は、その営業所の業務時間中に、何かあればすぐに対応できる状態でなければなりません。したがって、「名前だけ貸して」という形や、遠隔地に住んでいる親族などを管理者に立てることはできません。
▶ご参考:e-Gov法令検索 古物営業法 第十三条(管理者)
【ケース別】あなたのビジネスでは、誰が管理者になるべき?
管理者の選び方は、あなたのビジネスの形で変わってきます。
- ケース①:個人事業主・一人社長として自分で営業する場合 結論から言うと、この場合は「あなた自身」が許可者と管理者を兼ねるのが最も自然で一般的です。自分で全ての業務を行うのですから、当然ですよね。
- ケース②:複数の店舗(営業所)を展開する場合 法律では「営業所ごと」に管理者を一人選任することが義務付けられています。そのため、各店舗の「店長」が、そのお店の「管理者」を兼任するケースがほとんどです。
- ケース③:副業として自宅でせどりを行う場合 この場合も、本人が管理者を兼ねます。ただし、もし本業が日中のほとんどを会社で過ごすような勤務形態だと、「本当に自宅(営業所)を管理できるの?」と警察署から質問される可能性もゼロではありません。その場合は、自身の働き方や管理体制をきちんと説明する必要があります。
管理者の責任は重い?知っておくべき「3つの重要な役割」
古物商の管理者に任命されると、具体的にどのような責任と重要な役割を負うのでしょうか。主なものは以下の3つです。
役割①:不正品(盗品)の流入を水際で防ぐ
お客様から商品を買い取る際に、相手の本人確認が適切に行われているか、その品物が盗品などの不正品ではないか、といった点を従業員任せにせず、最終的に監督する責任があります。
役割②:「古物台帳」の適正な管理・記録
全ての取引を記録する古物台帳が、法律の定めに従って、漏れなく、正確に記載・保管されているかを管理します。これは、警察署の調査が入った際に、お店の正当性を証明する上で極めて重要です。
役割③:警察署との連携・協力
万が一、盗品に関する捜査協力の依頼が警察署からあった場合、その窓口となって誠実に対応するのも管理者の重要な役割です。日頃から、遵法意識の高い営業体制を築いておくことが求められます。
▶ご参考:警察庁 古物営業法
まとめ – あなたのお店の「守りの要」を決めよう
このように、「古物商の管理者」は、売上を作る店長とは違う、ビジネスの根幹である「法律遵守」を司る、まさに「守りの要」です。店長とは違うこの重要な役割を担う人物を誰にするかは、あなたのビジネスが長期的に、そして安全に続いていくかを左右する、非常に大切な決定なのです。
許可申請の際には、許可者本人の書類だけでなく、この管理者の「住民票」や「身分証明書」「略歴書」「誓約書」も必要になります。誰を管理者にするか早めに決めておくことが、スムーズな申請の第一歩です。
▶ご参考:神奈川県警察 申請に必要な書類
「自分のビジネスの場合、具体的に誰を管理者にすればいい?」 「副業なんだけど、常勤性についてどう説明すればいい?」
など、管理者の選び方に関する個別のご相談やご不安がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。元店長の視点も交えながら、あなたの状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
【ご注意】 この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。