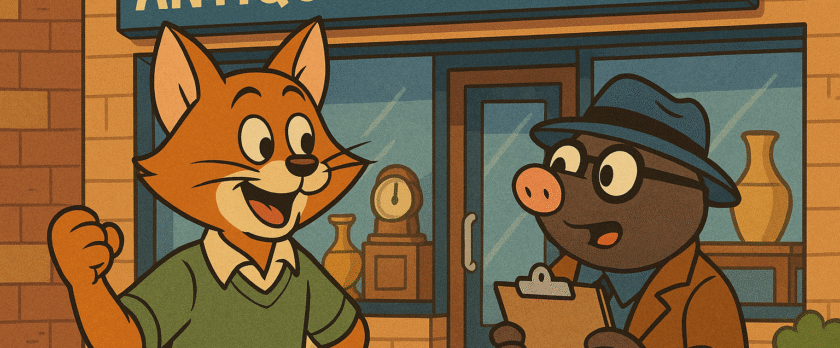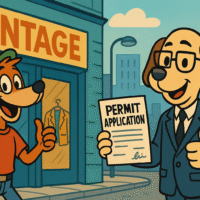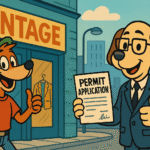「古物商の許可を取りたいけど、何から手をつければいいか分からない…」 「手順が複雑そうで、途中で挫折してしまいそう…」
その気持ち、痛いほどよく分かります。新しいことを始める時の手続きって、まるでゴールの見えない「すごろく」のようですよね。
こんにちは!あなたの冒険のナビゲーター、元「遊べる本屋」店長の行政書士・栗原です。
安心してください。この「古物商許可」という名のすごろくは、進むべきマスと正しいルートさえ知っていれば、誰でも必ずゴールにたどり着けます。時々現れる「1回休み」や「振り出しに戻る」といった厄介なマスも、この記事を読めば華麗に回避できますよ。
さあ、この記事という名の攻略本を片手に、古物商許可、申請から取得までの全ステップを、一緒に楽しく、そして確実に進んでいきましょう!あなたのための「完全ガイド」のスタートです!

【ステップ1:冒険の準備】申請前の自己分析と計画フェーズ
まず、いきなりすごろくのサイコロを振ってはいけません。最初のマスは「冒険の準備」。ここでしっかり計画を立てることが、ゴールへの最短ルートを築きます。
あなたはプレイヤーになれる?「欠格事由」のセルフチェック
そもそも、このゲームに参加できるかどうかの資格確認です。古物営業法には、残念ながら許可が受けられない条件(欠格事由)が定められています。例えば、「過去に特定の犯罪で刑罰を受け、その執行が終わってから5年経っていない」場合などが該当します。申請の前に、自分がこれに当てはまらないか、一度セルフチェックしてみましょう。 ▶ご参考:e-Gov法令検索 古物営業法 第四条(許可の基準)
どこに拠点(営業所)を置く?場所の確保と確認
次に、あなたの冒険の拠点となる営業所を決めます。これは自宅でも構いませんが、注意点が2つ。
- 賃貸物件の場合: 大家さんや管理会社から「営業所として使ってOK」というお墨付き(使用承諾書)が必要です。
- 分譲マンションの場合: 「管理規約」で営業活動が禁止されていないか、必ず確認しましょう。
どんな商人になる?「13品目」から専門分野を決める
そして、あなたがどんな商品を扱う商人になるかを決めます。古物には「衣類」「道具類」「書籍」など、全部で13の分類(品目)があります。将来的に扱う可能性のあるものは、この段階で全てリストアップしておくのが、このすごろくを有利に進めるコツです。
【ステップ2:アイテム集め】必要書類の完全リストと入手方法
準備ができたら、次はアイテム(必要書類)集めのマスです。この「完全ガイド」の核心部、以下のリストを参考に、一つずつ着実に集めていきましょう。
【古物商許可申請】必要書類一覧完全ガイド(個人申請の場合)
| 書類名 | 入手場所 | ポイント |
| 許可申請書 | 警察署の窓口 or ウェブサイト | 事前相談の際に貰い、書き方を教えてもらうのが最も確実です。 |
| 住民票の写し | お住まいの市区町村の役所 | 【最重要】「本籍地記載」で取得! マイナンバーは不要です。 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村の役所 | 運転免許証ではありません!「破産宣告等を受けていない」ことを証明する書類です。 |
| 略歴書 | 自分で作成(様式あり) | 過去5年間の職歴や住所歴を正直に記載します。 |
| 誓約書 | 自分で作成(様式あり) | 自分が欠格事由に該当しないことを誓う、自分自身との約束の書です。 |
| 営業所の使用承諾書 | 大家さん・管理会社 | 賃貸物件や、自分以外の人が所有する物件を営業所にする場合に必要です。 |
| URLの使用権限を疎明する資料 | 自分で準備 | HPやフリマサイトで営業する場合。「プロバイダ契約書のコピー」などでOK。 |
▶ご参考:警視庁 申請手続(古物商・古物市場主)(手続きの全体像が掴めます)
【ステップ3:いざ警察署へ!】申請書の提出と「立ち回り方」
アイテムが全て揃ったら、いよいよ警察署という名のダンジョンへ。ここでの立ち回り方が、申請から取得までの全ステップをスムーズに進める鍵となります。
アポ取りは必須!担当者とのファーストコンタクト
まず、いきなり窓口に突撃するのはNGです。担当者は他の業務で忙しいこともあります。「古物商の許可申請について、お伺いしたいのですが」と、必ず事前に電話でアポイントを取りましょう。丁寧な対応が、良い第一印象に繋がります。
窓口での心構えと「聞かれやすい質問」
窓口では、あなたのビジネスについていくつか質問されます。「どんなものを、どこで仕入れて、どうやって売るんですか?」といった、ごく基本的なことです。ここで必要なのは、誠実な態度。「遊べる本屋」も、事業計画をしっかり説明できたからこそ、周りの信頼を得られました。あなたのビジネスへの熱意を、正直に伝えましょう。
手数料を納付し、申請完了!
書類一式を提出し、内容に問題がなければ、手数料19,000円(※2025年7月現在)を納付して申請は完了です。お疲れ様でした!このステップ・バイ・ステップの旅も、大きな山を越えました。
【ステップ4:審査期間】「1回休み」の間にやるべきこと
申請が終わると、約40日間の審査期間という「1回休み」のマスに入ります。しかし、ただ休んでいるだけではもったいない!この期間は、来るべき営業開始に向けた絶好の準備期間です。
- 警察署の現地確認に備える: 担当者が営業所の状況を確認しに来ることがあります。申請内容と相違ないよう、いつでも見せられる状態にしておきましょう。
- 開業準備を進める:
- 標識(許可プレート)を注文する。
- 取引を記録する古物台帳(ノートやExcelでOK)のフォーマットを用意する。
- 具体的な仕入れルートや販売戦略を練る。
このように、待ち時間を有効活用することが、スタートダッシュ成功の秘訣です。
【ゴール!】許可証の受け取りと、その先の冒険へ
そして、ついに警察署から「許可が下りましたよ」という連絡が!指定された日に警察署へ行き、念願の許可証を受け取れば、すごろくはゴールです!
本当におめでとうございます! これであなたも、晴れて「古物商」の仲間入り。せどりも、自分のお店を持つ夢も、ここからが本当のスタートです。許可後の義務(三大義務や標識の掲示)をしっかり守り、信頼される商人として、新たな冒険を存分に楽しんでください!
▶ご参考:神奈川県警察 古物営業(許可後の手続きについても確認できます)
まとめ – あなただけの「すごろく」をゴールへ導くために
この「完全ガイド」で、古物商許可、申請から取得までの全ステップをステップ・バイ・ステップで解説してきました。
一つひとつのマスは、決して難しいものではありません。正しいルートと準備さえすれば、誰でもゴールにたどり着けます。この記事が、あなたの不安を解消し、自分でゴールまでたどり着くための羅針盤となれば幸いです。
もし、このすごろくの途中で道に迷ってしまったり、「このマスはどうしてもクリアできない…」と足止めを食らったりしたら、いつでもナビゲーターである私、栗原にご相談ください。あなたのゴールまで、最短ルートをご案内します。
【ご注意】 この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。